ゲーム=悪ではありません。
子どもと一緒に“納得して選ぶ・遊ぶ”ための、親のためのヒントをまとめました。
「このゲーム買っていい?」と聞かれて困ったこと、ありませんか?
子どもが急に言ってきた「○○ってゲーム、買っていい?」という言葉。
なんとなく不安だけど、詳しくは知らない。
友だちもやってるらしいし、断る理由もないけど、どこか引っかかる…。
「ゲームって依存しそう」
「暴力的な表現は大丈夫?」
「子どもに悪影響はないの?」
そんな気持ち、親なら一度は感じたことがあると思います。
この記事では、
ゲームを「禁止」ではなく「納得して選ぶ」ための視点を、
親の立場からお伝えします。
親がゲームに対して感じやすい不安
まず、ゲームに対して親が感じやすい懸念点を整理してみましょう。
長時間プレイしてしまうのでは?
時間を忘れて遊び続けてしまい、
生活リズムが崩れたり、宿題を後回しにしたり。
特にオンラインゲームは終わりが見えにくいため、心配になりますよね。
暴力的・過激な表現があるのでは?
一見かわいいキャラが出てくるゲームでも、
実は銃撃戦やホラー要素が含まれていたりします。
年齢に合わない刺激の強さは、
親として気になるポイントです。
オンラインで知らない人と関わる危険性
最近のゲームは、ネットを通じて他人とやり取りできるものが多く、
不適切な発言やトラブルに巻き込まれる可能性もゼロではありません。
ゲーム選びで大切にしたい3つの視点
「何を基準に選べば安心できるか?」
そのヒントを3つご紹介します。
内容の健全性(CEROレーティングをチェック)
CERO(セロ)というゲーム年齢区分マークをご存じですか?
A(全年齢対象)、B(12歳以上)、C(15歳以上)など、
ゲームには適切な年齢目安が記載されています。
特に C・D・Z(18歳以上対象)は、
子どもには不向きな表現(暴力・性表現など)を含むものもあるため要注意。
プレイスタイル(1人用?みんなで?)
ゲームによっては、
・1人でじっくり楽しむもの
・家族や友達と一緒に遊べるもの
などスタイルが異なります。
「友だちとやりたい」場合でも、オンライン対戦か、ローカル通信かで雰囲気は変わります。
“どう遊ぶか”もゲーム選びの重要な要素です。
時間・課金管理がしやすいか
親が把握しにくいのが、プレイ時間と課金の仕組み。
- オートセーブありで途中でやめやすい
- 課金要素がない or 制限しやすい
- 親のスマホからプレイ状況を確認できる
こうした「管理のしやすさ」も、安心材料になります。
おすすめの関わり方 3つ
ゲームを禁止するよりも、“一緒に向き合う”ことが大切です。
一緒に遊んでみる
最初は数分でもOK。
子どもと一緒にゲームを体験すると、
「どんな内容なのか」「どんな表現があるのか」がよくわかります。
「思ったより健全だった」
「逆に、これはちょっと気をつけたい」
そんな気づきが、実体験から得られるのがポイントです。
家族で“ゲームのルール”を決める
- 1日何分まで?
- ごはんや宿題とのバランスは?
- 約束を守れなかったらどうする?
親が一方的に決めるのではなく、
「一緒に考える」スタイルがおすすめです。
子ども自身が「自分で守る約束」を持つと、
意外としっかりルールを守ってくれることも。
「ゲームについて話せる関係」を保つ
「どんなゲームが好き?」
「今日は何が楽しかった?」
日常会話の中でゲームの話題を取り入れると、
子どもとの信頼関係が自然に育まれます。
「ゲームの話はいつも怒られる」ではなく、
「ちゃんと聞いてくれる」と思ってもらえることが、
健全なゲームとの関係をつくる土台になります。
まとめ:ゲームは「悪」ではない。付き合い方で未来が変わる
ゲームは、時代とともに進化しています。
勉強に使えるゲーム、運動になるゲーム、
プログラミングや創造力を育てるゲームも登場しています。
大切なのは、“禁止”ではなく“納得”。
- 何を選ぶか
- どう遊ぶか
- 誰と楽しむか
それを子どもと一緒に考えていくことこそ、
親にできる最も大きなサポートかもしれません。
ゲームを通じて、子どもとの距離が近づく。
そんな関わり方を、少しずつ始めてみませんか?

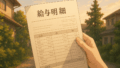
コメント