「他人の期待に応えなくていい」
「過去ではなく“今”を生きる」
「嫌われる勇気を持て」
アドラー心理学に出会ったとき、
その言葉は、まるで呪いを解いてくれる魔法のように響きました。
でも、ページを閉じたあと、ふと思ったんです。
**「これって、本当に私の考えだった?」**と。
今、自己啓発の本はあふれています。
SNSでも“前向きな言葉”が毎日のように流れてきます。
それ自体が悪いわけではありません。
私自身、たくさんの本や言葉に支えられてきました。
でも、ふと周りを見たとき、こんな違和感を覚えたことはありませんか?
「自己肯定感を上げたい」と言いながら、自分の価値を“数字”や“称賛”で測ろうとしている
「ポジティブでいよう」と言いながら、本当は傷ついているのに見ないふりをしている
「自分らしく」と言いながら、“誰かの正解”をなぞっているだけかもしれない
…もしかしたら、それは自身の姿だったのかもしれません。
特にアドラー心理学は、力強いメッセージを持っています。
読むと、一瞬、心が晴れたように感じることもあります。
でも実際には──
「そうは言っても、割り切れない」
「理屈では正しいけれど、感情がついてこない」
そんなふうに、モヤモヤしたことも何度もありました。
今回は、
そんな私自身の体験を通して、
**アドラー心理学の「よかったこと」と「受け入れきれなかったこと」**を、
ひとつひとつ丁寧に書いていこうと思います。
本に書いてある通りには、できなかった。
でも、自分の中で咀嚼して、自分なりの答えを出そうとしたからこそ、
今もこの考え方と向き合えている気がします。
「自分の頭で考える」ことを忘れたくない。
その想いを込めて、ここから書いていきます。

【アドラーの教え】 嫌われる勇気、幸せになる勇気 2冊セット
アドラー心理学の構造と目的
アドラー心理学が他の心理学と大きく異なる点は、
「人は変われる」「人生は自分で選べる」という前提を明確に持っていることです。
この考え方は、今の時代にとてもポジティブに映る反面、
その“根っこ”の思想をきちんと理解しておかないと、
表面的な自己啓発ワードとして消費されてしまう危うさもあります。
ここでは、アドラー心理学を形づくる5つの基本概念を簡潔に整理しながら、
「この理論は、そもそも何を目的としているのか」を確認しておきましょう。
① 目的論(原因ではなく目的に注目する)
フロイト心理学などが「人は過去のトラウマに影響される(原因論)」と考えるのに対して、
アドラーは「人は未来の目的に向かって行動している」と見ます。
たとえば、
「私は人付き合いが苦手なのは、子どもの頃にいじめられたから」ではなく、
「今、他人に傷つけられないように距離を取る“目的”がある」と考える。
これは、過去に引きずられずに“今ここから”を変えるための視点として、非常に力強いものです。
ただし、“原因”が持つ重みや事実を軽視してしまうリスクもあります(後述します)。
② 自己決定性(人は自分の生き方を選び直せる)
アドラー心理学の核とも言えるのがこの考え方。
「環境や過去ではなく、今の自分の選択が人生をつくっている」という前提です。
この考え方は、依存的な思考や被害者意識から脱し、
自分の人生を自分の責任で歩むという“主体性”を取り戻させてくれます。
ただしこれも、精神的・社会的に余裕のある人にとっては力になりますが、
支援が必要な立場にある人にとっては“自己責任の押しつけ”にもなりうる面があります。
③ 課題の分離(何が誰の責任かを明確にする)
これは実生活で最も応用しやすく、また誤解されやすい考え方のひとつです。
「これは自分の課題か?他人の課題か?」を見極め、
他人の課題には踏み込みすぎず、自分の課題には責任を持つという視点。
たとえば、
子どもが勉強しないのは「親の課題」ではなく「子どもの課題」だと分けて考える。
これは、相手を尊重し、自分を守るための線引きとして非常に有効です。
ただし、誤って使うと「ドライ」「冷たい」と誤解されたり、
本来必要な支援まで手放してしまうリスクがあります。
④ 承認欲求を否定する(他者評価から自由になる)
アドラーは「人は誰かに認められようとして生きてはいけない」と言います。
その代わりに提唱されるのが「共同体感覚(他者貢献の意識)」です。
つまり、「評価されること」ではなく「役に立てること」が人の幸福をつくる、という考えです。
これは、現代のSNS社会の中で「承認疲れ」を感じている人にとっては、
非常に救いになる視点でもあります。
しかし、人が持つ「認められたい」という自然な欲求を一律で否定するように読まれてしまうと、無理を感じる人も少なくありません。
⑤ 共同体感覚(人とのつながりを意識する)
アドラー心理学は、個人主義ではありません。
むしろ「他者貢献」や「信頼」「対等な関係」を重視します。
人は孤立した存在ではなく、誰かと協力し、支え合う中で自己を確立していくという視点。
この共同体感覚は、アドラー心理学の最終目標ともいえる考え方です。
▶ アドラー心理学の目的とは?
ここまでの概念を整理すると、
アドラー心理学は単に「ポジティブに生きよう」と言っているわけではありません。
「自分の人生に責任を持ち、他者と対等な関係でつながりながら、幸福を目指す」
──それがこの理論のめざすゴールです。
しかし、現代の「自己啓発文化」の中では、
この全体構造を理解せずに“刺激の強い言葉”だけが切り取られがちです。
「嫌われる勇気」や「承認はいらない」というフレーズは、
一部だけ見ると過激で、冷たくすら見えるかもしれません。
だからこそ、この章で触れたような“土台の思想”を理解したうえで、
メリットも、デメリットも、丁寧に見ていく必要があるのだと思います。

アドラー心理学がマンガで3時間マスターできる本
アドラー心理学の“使えるメリット”10選
アドラー心理学は、単に「前向きになれる言葉の詰め合わせ」ではありません。
その本質は、“自分と他者の関係をどうとらえるか”という視点の変化にあります。
ここでは、私自身が実際に「これは生活に活かせる」と感じたポイントを、
実用スキルとして捉え直しながら紹介していきます。
① 他人の感情を「自分の責任」と思わなくなる(課題の分離)
スキル的解釈:他者の反応に必要以上に左右されず、冷静に判断できるようになる。
アドラー心理学が教える「課題の分離」は、
「それは誰の問題か?」を見極める思考法です。
たとえば、誰かが怒っているとき。
それは必ずしも自分のせいではなく、相手の内側の問題である可能性もある。
そう思えることで、自分を責めすぎたり、過剰にコントロールしようとする負担から解放されました。
🔍 この視点を身につけると、感情的な巻き込まれ方を減らすことができます。
② 自分の「選択」に意識が向く(自己決定性)
スキル的解釈:「なぜそれを選んだのか」と自問できる視点が持てる。
人は環境や人間関係に左右されながら生きています。
でもアドラーは、「最終的にどう振る舞うかは、自分が選んでいる」と見ます。
これはつまり、**「私にはいつでも選び直す自由がある」**ということ。
習慣・人間関係・感情の向き合い方すべてが、変えられる可能性を持っていると気づくことは、
変化への第一歩になります。
🔍 「誰のせい」ではなく、「どうするか」で考えるくせがつきます。
③ 承認を求めすぎなくなる(承認欲求からの自立)
スキル的解釈:行動の基準が「他人」ではなく「自分」に戻る。
人は誰しも、誰かに認められたいという欲求を持っています。
でもそれが過剰になると、評価が怖くて動けなくなる。
アドラー心理学では「人に褒められることを目的にしない」という姿勢をとります。
これは「承認を捨てる」ことではなく、行動の主語を“自分”に戻す技術です。
🔍 他人の反応ではなく、自分の「納得感」を判断基準にできるようになります。
④ 「今この瞬間」に集中できるようになる(目的論)
スキル的解釈:過去ではなく、今の意図に目を向けて行動できる。
アドラーは「行動はすべて“目的”を持っている」と捉えます。
「過去のせいでこうなった」と思うのではなく、
「今、自分はこうしたいからこうしている」と考える。
それは、過去に引きずられずに**“現在の自分”に責任を持つ力**を育ててくれます。
🔍 後悔にとらわれるよりも、「今、何をしたいのか」にフォーカスできるようになります。
⑤ 人間関係に線を引く視点が持てる(信頼と干渉の違い)
スキル的解釈:相手に介入せず、でも信頼を持って関われる。
アドラー心理学の特徴のひとつは、「支配しない関係」です。
人を変えようとせず、「相手の課題は相手が解決する」と信じて任せる。
これは、放任とは違います。
信頼して見守る、という姿勢に切り替える技術です。
🔍 コントロールしようとする癖から解放され、人間関係がシンプルになります。
⑥ 自分の行動に「意味」を持たせられるようになる(目的の再定義)
スキル的解釈:何となくやっていた行動に、自分なりの目的を与え直せる。
アドラー心理学では「行動には目的がある」と捉えるため、
日常の小さな行動にも「なぜそれをするのか?」と問いを立てる癖がつきます。
それは、行動の背景を整理し、**「惰性ではなく、選択として動く」**ことに近づけてくれます。
🔍 意味のない努力に振り回されず、やるべきことを絞り込めるようになります。
⑦ ネガティブ感情に巻き込まれにくくなる(感情の目的論)
スキル的解釈:落ち込んだ自分を「否定せず分析」する視点が持てる。
アドラーは、怒りや悲しみ、落ち込みさえも「何かの目的がある」と考えます。
「なぜ落ち込んでいるのか」を責めるのではなく、「何を避けようとしてる?」と掘り下げる視点があると、感情に呑まれにくくなります。
🔍 自分の感情に「距離」を取れるようになり、冷静さを保ちやすくなります。
⑧ 人と“横の関係”で接する意識が持てる(上下関係の否定)
スキル的解釈:自分を卑下せず、相手を持ち上げすぎない視点が育つ。
アドラー心理学では、「上下関係ではなく、対等な“横の関係”」を重視します。
これは、人を敬うことと、自分をおとしめないことのバランスを学ぶ機会になります。
たとえば、上司に萎縮したり、後輩に対して威圧的になる自分に気づいたとき、
「人としては対等」という原則を思い出すと、余計なストレスが減ります。
🔍 自分を大きく見せたり、小さく見せたりする必要がなくなります。
⑨ 「貢献」を意識することで、
自分の存在意義を感じやすくなる(共同体感覚)
スキル的解釈:誰かの役に立つ=自己肯定感につながる構造が理解できる。
アドラーは、幸せの本質を「共同体感覚」にあるとします。
つまり、「誰かの役に立っている」と感じられること。
これは「承認」とは違い、評価されるかどうかではなく、自分が社会の一部であるという感覚です。
孤独感や無力感が強くなる現代で、この感覚を持てることは、心の安定に大きく影響します。
🔍 承認欲求に縛られずに、自分の価値を実感できるようになります。
⑩ 「今のままでもいい。でも変われる」と
思えるようになる(自己決定性+希望)
スキル的解釈:現実を受け入れながら、変化の余地を肯定的に捉えられる。
アドラー心理学は、「変われる」というメッセージを強く打ち出します。
ただそれは、「今の自分を否定しろ」という意味ではありません。
「今のままでも、ここからどう動いてもいい」
この柔軟な視点が、焦らず自分のペースで進む力を育ててくれます。
🔍 “現状肯定”と“未来志向”を両立できる思考法になります。
▶ アドラーの“言葉”を“スキル”として使うために
ここまで紹介した10のポイントは、
どれも「名言を知る」だけでは身につきません。
- 日々の会話
- 自分との対話
- 人間関係での選択
そんな場面で「どう使うか」「どう意識するか」を通して、少しずつ自分のものになっていきます。
重要なのは、受け身で“教えを受け取る”のではなく、能動的に“使ってみる”ことです。
アドラー心理学の“受け入れきれなかったところ”10選
アドラー心理学は、
シンプルで、前向きで、強く生きるための指針をくれます。
でも──
それゆえに、ときに人の弱さや現実の複雑さを“すくいきれない”場面もあります。
私自身も、実践するなかで「ここはちょっと苦しかった」と感じることがありました。
この章では、その「モヤモヤ」に正直に向き合いながら、
誤解されやすい点やリスクを、読者と一緒に考えていきたいと思います。
① 「嫌われてもいい」は、本当に難しい
嫌われる勇気──この言葉は象徴的ですが、
実際にそれを実践するのは想像以上に難しい。
仕事・家族・友人…私たちは誰かとの関係性のなかで生きています。
関係を壊す恐れと背中合わせの“勇気”を、
毎回持てる人はそう多くない。
🔍 自己主張の大切さと、人間関係の繊細さ。その間でバランスを取ることが大切です。
② 承認欲求を捨てるのは、現代ではかなり無理がある
「他人に認められたいと思ってはいけない」──
これは現代のSNS社会と真っ向からぶつかります。
人は「評価」や「いいね」によって繋がる世界で生きています。
承認欲求は否定するものではなく、上手に扱うものではないでしょうか。
🔍 否定ではなく、「自分で満たす方法」「軸を整える方法」を学ぶ方が現実的です。
③ 課題の分離が「冷たさ」に見えることがある
「それはあなたの課題です」は、言い方によっては突き放す印象を与えます。
ときには“無関心”や“責任放棄”と受け取られることも。
特に家庭・職場・介護・育児など、距離が近く逃げられない関係性では、
この考え方をどこまで適用すべきか悩みます。
🔍 線を引くことと、寄り添うことは両立できる。その工夫が必要です。
④ 誰にでも「自分の人生を選ぶ力」があるとは限らない
アドラー心理学の前提には「自己決定性」があります。
でも、経済的・身体的・心理的に自由を持てない状況も世の中にはある。
「あなたの選択です」と言い切ってしまうことは、
ときに“自己責任論”に近くなる危うさもあります。
🔍 理論の強さは、状況によって人を追い込む力にもなりうると知っておくべきです。
⑤ 感情を“目的”で説明しすぎると、気持ちが軽視される
「怒りは相手を動かすための手段」など、感情を目的で説明する考え方は一理あります。
でも、実際には感情はもっとぐちゃぐちゃしていて、言語化できないこともある。
🔍 感情を機能的にとらえる前に、「感じることを許す」余白も大事です。
⑥ 自分に厳しくなりすぎる可能性がある
アドラー心理学を真面目に取り入れる人ほど、
「自分で選んだことだから」と、すべてを自責で処理しようとしてしまう。
それは成長の一歩かもしれないけれど、弱音や逃げ道を封じてしまう危うさもある。
🔍 「選んでいる」と同時に「選べないときがある」ことも、自分に許していい。
⑦ 「目的論」では説明しきれない現実もある
アドラーは「人の行動はすべて目的がある」と考えますが、
ときに人は理由もなく落ち込むし、意味のない選択をしてしまうこともあります。
すべてに理由を求めることで、かえって自分を追い詰めることも。
🔍 「目的を探す」より「ただ感じて受け流す」方がいい時もある。
⑧ 上司・親・権威のある立場の人が使うと、関係を壊すことがある
「課題の分離」や「自己責任」の考え方は、
立場の強い人が使うと、「押しつけ」や「切り捨て」に映ることがあります。
相手がアドラー的思考を知らない場合、余計にすれ違いを生みやすい。
🔍 この考え方は、“相互理解”が前提。片側だけの実践には限界があります。
⑨ すべてが「自分の選択」で片づけられると、つらい
「あなたが選んだ結果です」と言われて、
救われることもあれば、突き放されたように感じることもある。
人は、選べなかったことも、流されただけのことも、ある。
🔍 人生には「流されるしかなかった時期」もあっていい。その事実を抱えたままでも、前を向ける。
⑩ すべてを自分で決めるのは、疲れる
アドラー心理学は「自立」や「選択」を強く推しますが、
常に「自分で考え、自分で選ぶ」ことは、正直しんどい。
人に頼ったり、流されたり、感情に身を任せる日があってもいい。
それを“悪いこと”だと切り捨てる必要はないと思うのです。
🔍 自立は大切。でも「寄りかかれる場所があること」も、人として健全なことです。
自己啓発との付き合い方──自分で考える力を取り戻すために
アドラー心理学を学んで、私自身とても多くの気づきをもらいました。
でも同時に、「これは考えずに飲み込むと危ないかもしれない」と思ったことも、正直たくさんあります。
それは、アドラーに限らず──
あらゆる「自己啓発」の世界に共通して言えることかもしれません。
自己啓発は“答え”ではなく“問い”であるべき
本を読む。
誰かの言葉に救われる。
大事なことです。私も何度も救われてきました。
でも、そこに書かれていた言葉を「正解」として受け取ってしまったとき、
自分の思考や感情を置き去りにしてしまう危うさがあります。
たとえば──
- 「嫌われてもいい」と書いてあるから、本当は怖くても突き放してしまった
- 「自分で選んだ人生」と言い聞かせて、本当は助けてほしかった気持ちにふたをしてしまった
- 「感情には意味がある」と信じすぎて、ただ感じることが怖くなってしまった
そんなふうに、「言葉に従う」ことで、本当の自分から離れてしまうことがある。
🔍 自己啓発の言葉は、「考えさせてくれる問い」であってほしい。
その言葉に、“自分なりの意味”を与えられたとき、初めて力になる。
すべてを鵜呑みにしなくていい。合わない部分は、手放していい。
どんなに有名な理論でも、
どんなに人気のある本でも、
「全部が自分に合う」なんてことは、まずありません。
それでも、「全部正しい」と思い込んでしまうのは、
たぶん、“正解を外に求めすぎているとき”です。
自己啓発は、あなたを正しくするものではなく、あなた自身に戻るきっかけになるもの。
だから、合わない部分は受け入れなくていい。
響いた部分だけ、自分の言葉にして使えばいい。
自己啓発に「頼る」より、「活かす」スタンスで
私は今でも、アドラーの考え方が好きです。
だけど、それに「従って」いるわけではありません。
あくまで、「使っている」だけです。
- 使えるところは使う
- 使えないときは、いったん保留する
- 使ってみて合わなければ、違う視点も持つ
そんな**“自分が主導権を持ったスタンス”**でいること。
それが、自己啓発に振り回されないコツだと思っています。
正解を探すのではなく、「自分で考える練習」を続けよう
今回、アドラー心理学というひとつの理論を通して、
「自分の思考力を育てる」ことについて書いてきました。
たとえ答えが見つからなくてもいい。
「私はどう思うか?」「本当にそうか?」と立ち止まる力が、
今の時代、何よりも大切なのだと思います。
まとめ
- アドラー心理学には、実生活に役立つ考え方がたくさんある
- でも、それが「絶対の正解」ではない
- 限界やリスクも知ったうえで、自分の判断で活かすことが大切
- 自己啓発の言葉に“従う”のではなく、“考えるきっかけ”として使おう
自己啓発は、自分の思考を深めるための「道具」であって、
心を空っぽにして従う「指示書」ではありません。
これからも、誰かの言葉に出会ったとき、
そのまま受け取るのではなく、
“自分で考えて選び取る”あなたでいられるように。
その願いを込めて、この記事を終わります。
🌿最後まで読んでいただきありがとうございました。
・この記事を読んで、感じたことや考えたことがあれば、ぜひコメントで教えてください。あなたの視点も、きっと誰かのヒントになると思います。
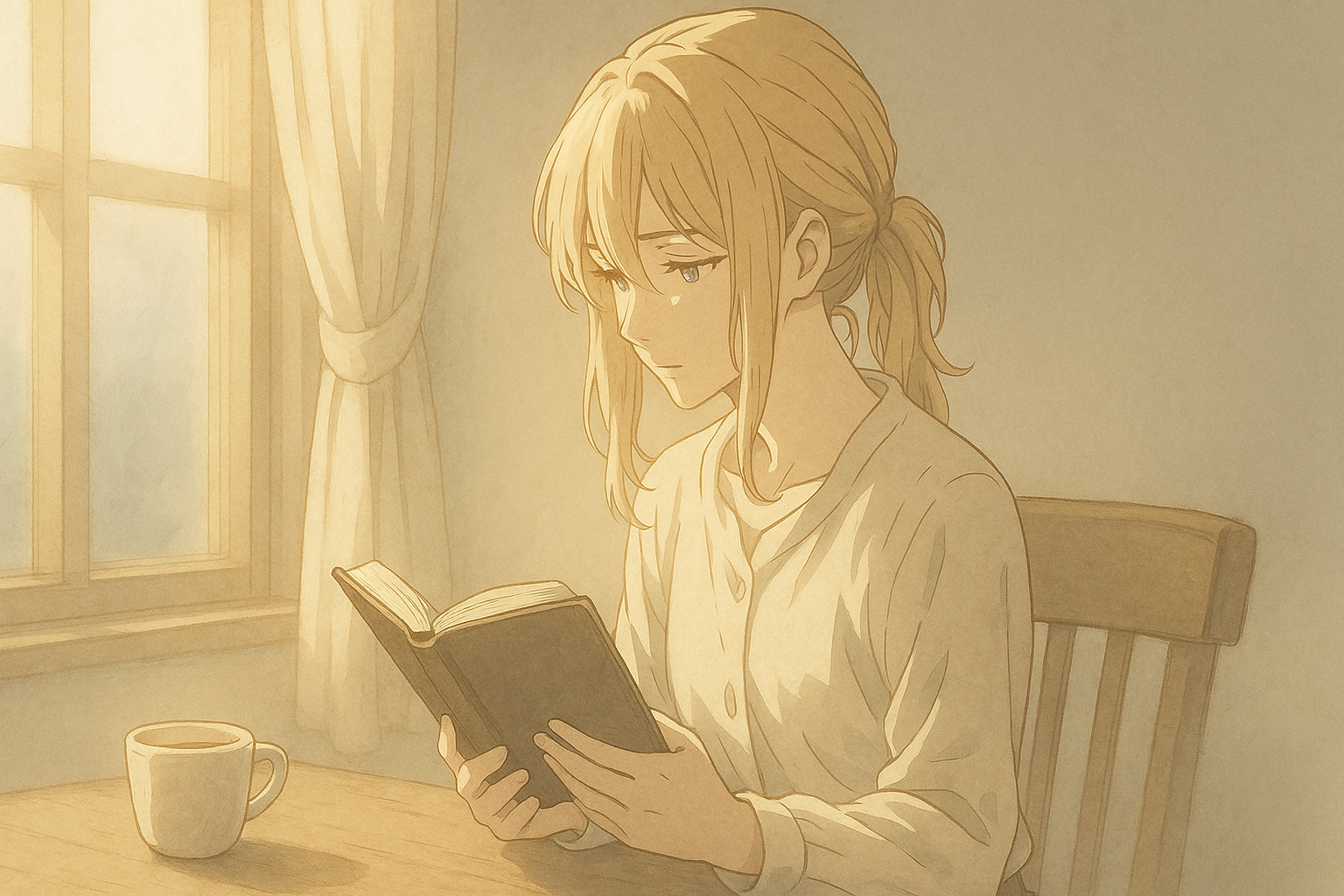


コメント